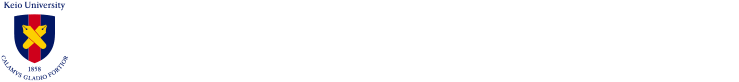三四会概要
会長挨拶
『慶應義塾大学医学部三四会』は、初代会長に北里柴三郎博士を迎え、1920年1月に学生の活動として発足しました。現在は医学部の同窓会として、2020年に発足百周年を迎えました。
三四会の会則には、<目的>として、「本医学部と密接な連携を保ち,会員相互の親睦,医学医術の研鑽に努め,福澤,北里両先生建学の訓えを体して慶應医学の隆盛発展に寄与することを目的とする」と書かれています。
同窓会は卒業生の懇親の場でありますが、慶應義塾には福澤先生の「社中」として、卒業生でなくても仲間として迎え入れる考え方があります。また、医学部の同窓会は、医療に携わり、社会に貢献している医師・歯科医師の集まりで、この事は他の同窓会との大きな違いと言えます。さらに三四会は、患者の紹介や治療内容の指導などだけでなく、医師の生涯教育の場として、また医学部の学生教育にも貢献してきました。
慶應の医学科の設立は1917年ですが、開校・開院式が行われたのは1920年11月でした。北里柴三郎博士は、開校・開院式で「基礎医学と臨床医学との懸隔を努めて接近せしめる方針である。学部は恰も一家族の如く、教授も講師も助手も一致協力して」と、設立する医学部の基本的姿勢を述べていることは周知の所です。牢乎たる医学部・病院の設立には、社中の一致協力が必須の条件でありました。また、1919年4月の信濃町での始業式では、「本大学の将来に期する所は、私学としての医学を発達せしむるに言を待たず」と、抱負を述べています。
大学教育の目的は人材育成であり、医学部で教育を受けた学生が卒業すると同窓会員となります。したがって、同窓会は大学の人材育成の成果そのものと言えます。すなわち三四会は、慶應の医学教育の成果の集積であり、三四会員の社会的評価は慶應義塾大学医学部の教育の評価ということになります。また、三四会員は慶應義塾大学医学部の卒前・卒後教育に大きく関わり、三四会員全員で慶應医学を育んでいます。三四会は慶應義塾大学医学部と強く結びついており、互いに表裏一体の関係にあると言えます。
慶應義塾大学医学部は百年を経て、北里の訓えとして基礎医学と臨床医学、診療科間などの横への繋がりが、先輩から後輩へ、医学部から同窓会へと年代を超えての縦の繋がりをもって受け継がれてきました。三四会の強みは、この縦糸と横糸が編み出してきた組織力の強さと言えます。それは、福沢精神と北里博士の訓えの元に、学生時代から培われた愛校心が、その根底にあって集結してきたことによると考えます。
今後三四会が、福澤,北里両先生建学の訓えを体して慶應医学の隆盛発展に寄与して、一層強固な組織となるために、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
令和5年6月
武田純三